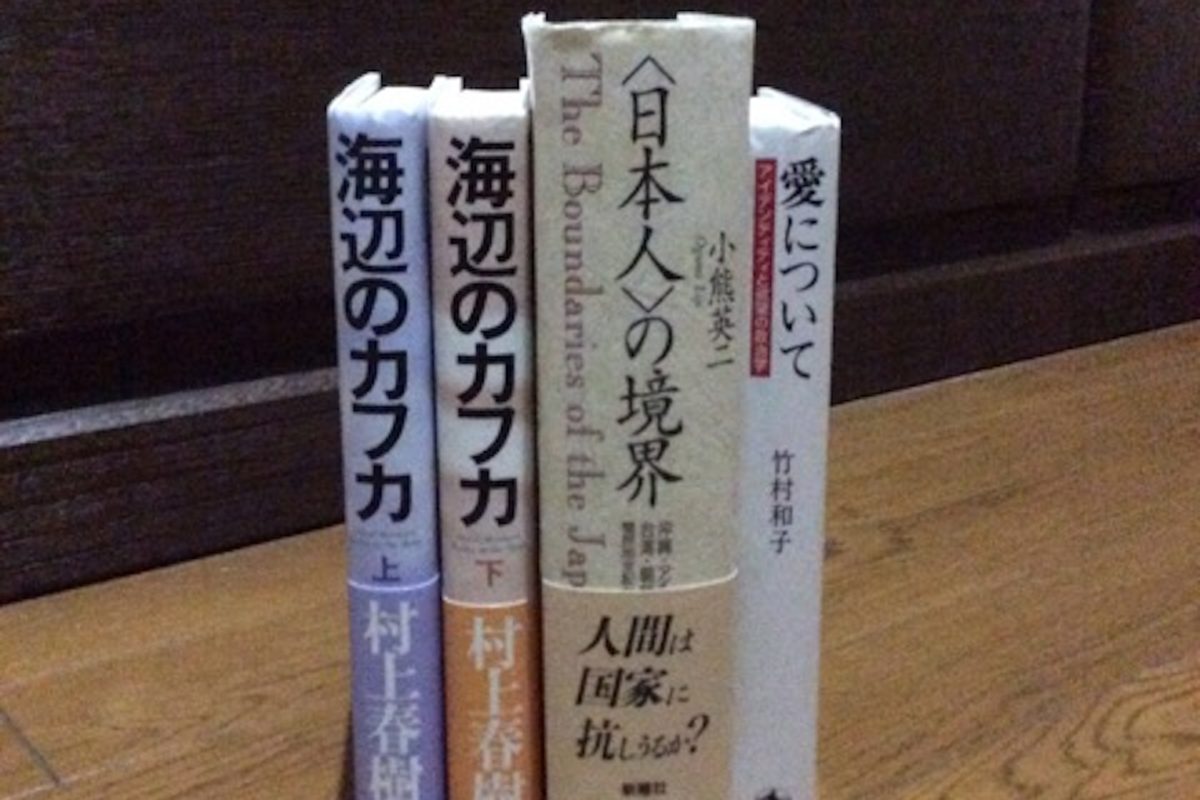これまで、僕たちは、犯罪と、貧困を、世界の脅威と、認識してきた。それらから、社会を守るために、手段を、講じてきたのである。ときに、犯罪と貧困が、増加していくのは、劣った遺伝子を持つ人々が、多くいるからだと、考えられた時代も、あった。階級間での、知能の差異が、取り沙汰されたのである。
★ ★ ★
・ジェノサイド、あるいは忘却の彼方へ
歴史を振り返ってみれば、人間は、数多くの、残酷なことを、してきたのではないだろうか。戦時中において、多くいれば、社会が、進歩する妨げになるとして、障害者の安楽死が、行われたり、特定の人種を、抹殺しようとしてきたのだ。
それらの行いが、悪であるのは、言うまでもない。けれど、問題がある/ないという境界は、曖昧なままで、もし、殺人が、行われないとしても、その時代の悪を、引きずっているのであれば、その行いを隠そうとする。少なくとも、繋がりのありそうな行いを、控えようとする。表に出さないようにする。
こうして、空白の時間の中で、戦時中の行いが、忘却の彼方へ、消え去ってしまうのではないのだろうか。どこまでが、自明な悪なのか、はっきりさせ、検証していくことは、必要だと思う。
・多様性、あるいは文句を言う
人種や、性別によって、就労の機会が、平等でなくなるのは、よくない。一部の人間を、排除することによって、社会を、円滑に、進めようとする考え方も、おかしい。現代において、「多様性」の重要性が、叫ばれるのにも、そこに、意味があると思う。
実際は、一人残らず、誰もが、現状に、満足しているのだろうか。環境によって、左右され、可能性が、狭められていることはないのか。誰かが決めた基準によって、能力が低いと、評価され、就労の機会を、失っている人は、いないのか。宗教や、人種によって、差別されている人は、いないのか。そうだとしたら、なぜ、誰も、文句を言わないのだろう。
★ ★ ★
たしかに、開始点においては、未来は、可能性に満ちている。けれど、同時に、あらかじめ、その可能性を、本人は、知り尽くすことはできない。どれだけ、努力すれば、どれだけの見返りが、あるのか、全く分からない。やればできるかもしれないという希望が、利用されているのである。
けれど実際、努力すれば、いくらかは報われることを、知っているし、もっと言えば、自分の努力で、どうにもならない部分が、あることも知っている。葛藤を抱えたまま、すべては、個人の責任になって、返ってくる。これは、かなり、巧妙な、社会の仕掛けみたいだ。