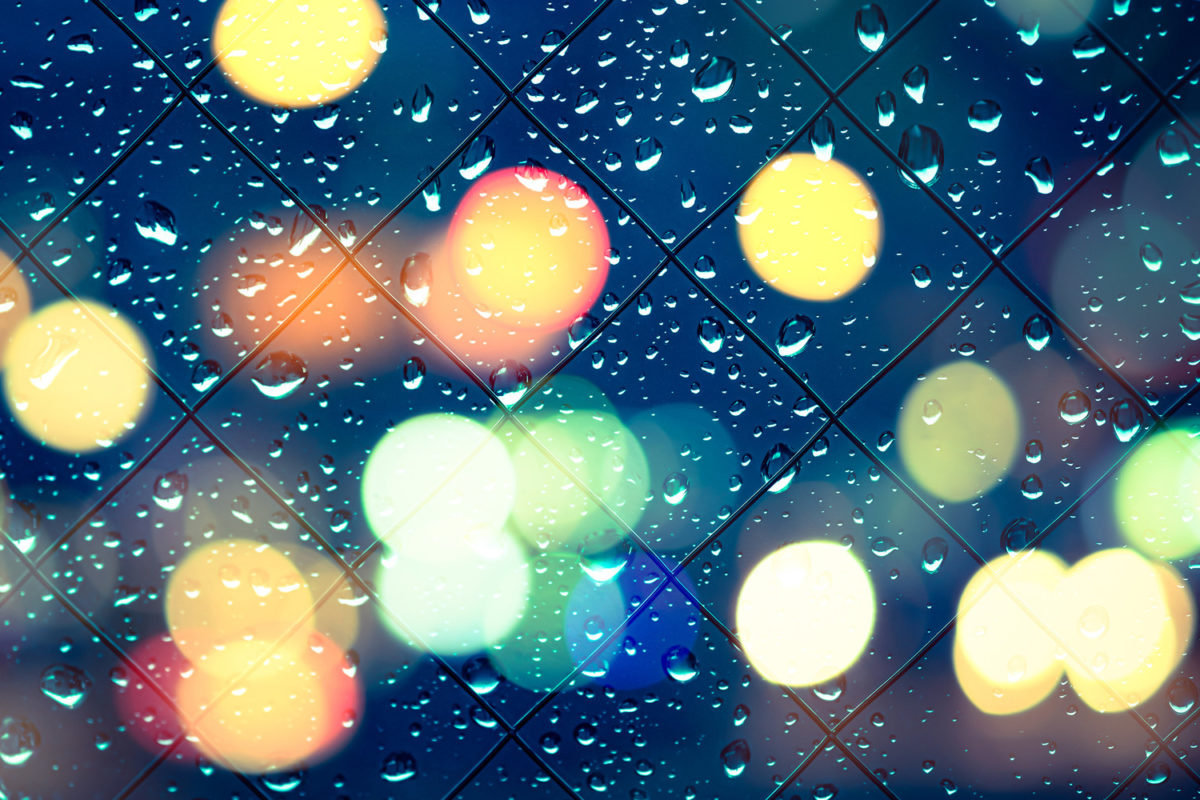<基本情報>
2011年に、イギリスで制作された作品。
監督は、「荒野にて」「さざなみ」の、アンドリュー・ヘイが、務める。
2人の男性の、距離が近づいていく過程を、繊細なタッチで、描く。
「エモい」という言葉がある。英語の「emotion」が、形容詞化したものらしい。どういうときに使うのか、あまり分からない。だけど、この作品を、一言で、表現するなら、そのワードだと思う。全体に流れる雰囲気が、いちいち、感情に訴えかけてくる。仕事におわれながら、孤独に過ごす毎日。気兼ねなく過ごす、友人同士でのパーティー。心が浮つく、週末。どの時間も、間違いなく自分なんだけど、それぞれでわき起こる、ことなる感情や、心情。その微妙な変化を、軽やかに、映し出していく。
自分に自信を持てず、内向的なラッセル(トム・カレン)。それとは、対照的に、ゲイであることを、隠さないグレン(クリス・ニュー)。いっけん、相性の悪そうな2人が、同じ時間を過ごしていくうちに、お互いが、何を大切にして生きているのかを、知っていく。マイノリティーへの、偏見や差別を、なくそう。だけど、なぜ、それらの行為を、してはいけないのか。その理由を、理屈ぬきで語る。それを、さらっと積み上げていく、ラディカルな視点が、垣間みられる。
男性同士の、恋愛。それについての、イメージは、ひとり一人、違うと思う。肉体関係だけの、つながり。あるいは、プラトニックのような、精神的な結びつき。だけど、例えば、異性同士の恋、女性同士の恋との、相違点を、言葉で、定義するのは、とても困難だと、思う。たぶん、どの場合にも通ずる、人間の奥に潜む愛情。お互いの性質を、尊重し、理解していく行為は、自分自身を、変えていく。この映画は、あたり前のように、出会いと別れを繰り返す、僕らの普遍性についての、物語だ。