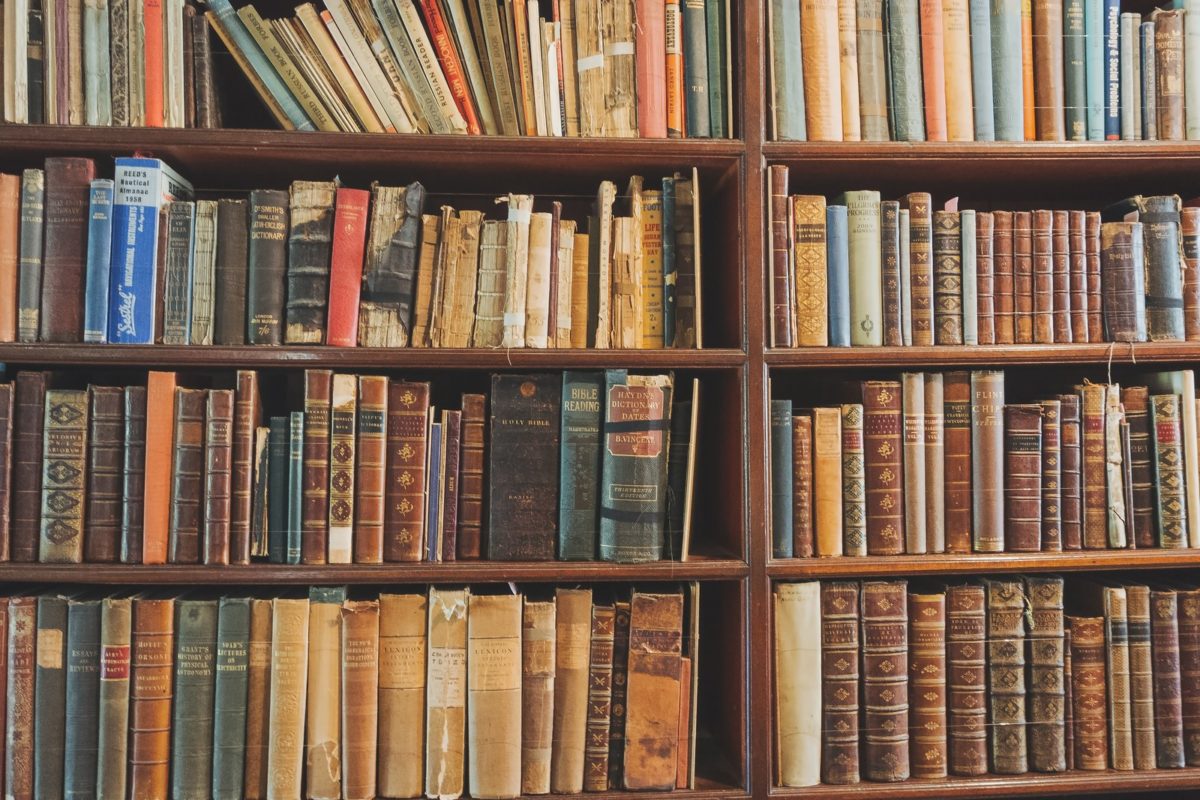<基本情報>
第89回アカデミー賞で、作品賞、脚色賞、助演男優賞の3部門を受賞。
キャストには、「007」シリーズのナオミ・ハリス、テレビドラマ「ハウス・オブ・カード 野望の階段」のマハーシャラ・アリという名俳優たちが、揃う。
製作総指揮は、アクターとしても評判の高い、ブラッド・ピッドが、務める。
LGBT、ジェンダー、マイノリティー、次々と生まれる概念は、果たして、人間を生きやすい方へと導いてくれたのか。普通と特殊との間に線引きをして、区別していくことで得られる安心は、幻想じゃないかと思えてくる。その人自身に問題があるとか、ないとかの判断は、たぶん誰にもできない。あくまでも傾向として、それぞれを捉えることができたら、互いの理解に繋がっていく。この社会が、どんなふうにあるべきかを問うことは、ひとり一人が抱える生きづらさと真正面から向き合うことと、同義だと僕は思う。
マイアミの貧困地域で暮らすシャロンは、小柄な体格のおかげで、周りから「リトル(チビ)」と呼ばれている。男の子は、男の子らしく振る舞うべきだという規範は、一見あたり前のように感じる。そこから外れる者は、排除されてしかるべきだというのは、間違っている。性が倒錯してしまうことに、一抹の不安を覚えるかもしれない。だけど、もう、すでに、性的少数者の問題は、人権課題として認識されている。いまさら多様性を、蔑ろにするほうが、違和感がある。女の子らしく行動する男の子が、いてもいい。それを、受け入れることができるのは、これからを生きる、まぎれもない僕たちなのだ。
黒人の同性愛をテーマにすることに、なんの意義があるのか。ゲイとして生きること、黒人として生きること、母子家庭に生まれること、薬物に向き合うこと、貧困のさなかで、なにが大切かを知ること、それらすべてが、この映画に組み込まれている。月明かりのしたで、友情以上の感情に、戸惑いながらも、互いの距離を近づけていく場面は、きっと、情緒性に満ちている。少年から、大人になっていく過程で、彼らの容貌も、性格も、生活環境も、大きく変化する。だけれども、変わらない「愛」が、そこには、あった。たぶん、どんなに悲観的なことが起きても、けっして揺るがない、特別な思いを再発見できる。